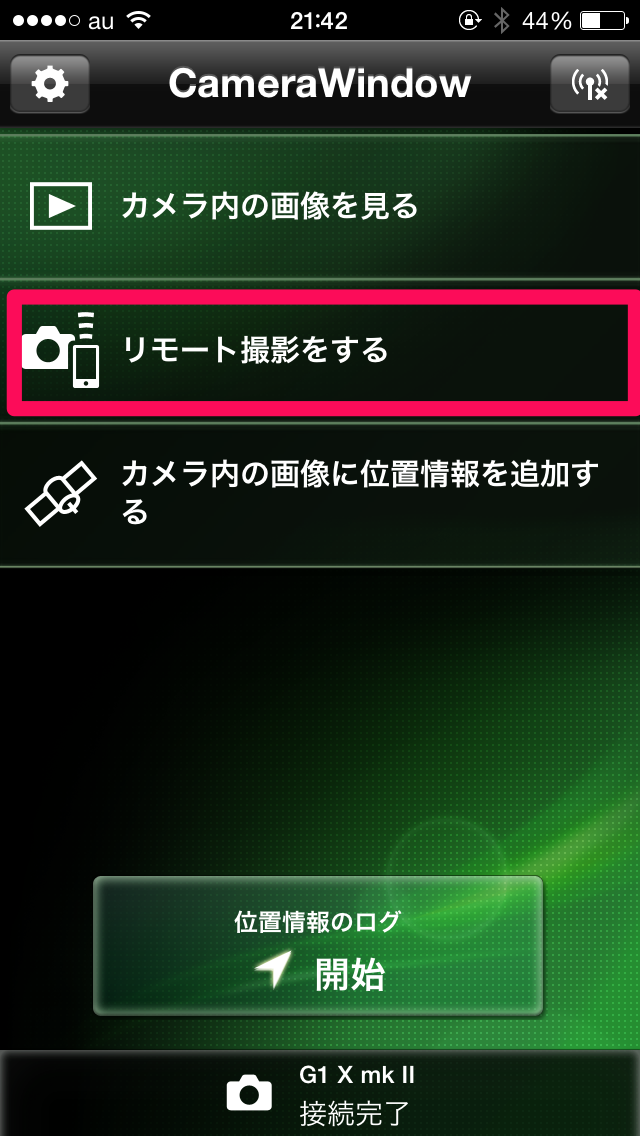ヨドバシカメラで実物を操作して良さそうだったので買おうと思ったのですが在庫無しとの事でその場でAmazonでポチッと行ってしまいました。
EVFとしての性能
カタログなどで全くスペックが公開されていないのですが水準器のドット感が全く同じなので背面液晶と同じ解像度じゃないかなと思います。
実質ミラーリングだけど、近接センサーでどちらか片方にしか出力されない様に制御されている。そんな感じ。
背面液晶と同じと考えると他社EVFと比較すると解像度はあまり高くないのかな?って気もします。スペックを公開出来ないのもなんとなく頷ける。
誤情報ごめんなさい、海外の方ではスペックが公開されているみたいです。
 Canon EVF-DC1 Electronic Viewfinder:Amazon:Camera & Photo
Canon EVF-DC1 Electronic Viewfinder:Amazon:Camera & Photo
このファインダーはXGA解像度らしいですが、オーバーレイ表示されるメニューやアイコン等は背面液晶と同じ密度で描画されて、受光した映像はXGAで表示されるのだと思います。
とすると、EVFへの表示が切り替わるのが若干遅いのもちょっとだけ許せる気になってきました。
下はEVFの映像をS95で撮ってみました。写真ではゆがんで撮れてしまいましたが、目で見ると綺麗な矩形に見えます。


解像度に不安があるとは言え実用十分という感じで、微妙な角度で撮られた直線的な構造物の写真をプレビューで見ると窓枠などにわずかにギザギザを感じる位です。
が、私は視力が良いので見えてしまうのだと思いますが気になるレベルではないです。
また一般的にEVFは視像の表示遅延が問題になることがあるようですが使ってみた感じそのような感じは全くありません。
悪い点
このEVFを装着すると大きなコンデジがますます大きくなります。G1X mk2とうまく付き合う為には大きさ、重さは避ける事の出来ない課題ですね。
あと近接センサーにより排他的に背面液晶とEVFの表示が切り替わるのですが切り替わりが遅いです。
ファインダーを覗き込むと一瞬暗黒面が見えます。
EVF装着時はEVFにしか映像を出力しない、みたいな設定があると嬉しいのですが探してみた感じ見当たりません。
EVFは消費電力が大きいらしいのでメーカーとしてはそのような使い方を許したくないのかもしれないですね。
もう一点、EVF側面に付いてる切り替えボタンが無用の長物という…。役に立たないとわかっているボタンなら無理に実装しようとせずにコストダウンなり他の部分の性能向上なりに務めて欲しい所です。
良い点
コンパクト性を無視したその大きさが逆に撮影時にメリットに転じます。
アホか!コンデジに一眼レフのファインダー付けるなよ!って言いたくなるくらいの大口径ファインダー。

見よ、この携行性を無視した贅沢な空間の使い方。

目をすっぽりと覆い隠してくれる大きなファインダーである事は個人的に非常に嬉しいです。なぜならば私は明るすぎる場所でファインダーを活用したいというのがいちばんの目的なので。
ファインダーのフードが深いのでよっぽど密着させない限りまつ毛が干渉しないですし、ファインダーが本体よりも後ろに出っ張っているので、本体と鼻が接触することもありません。
そもそも目に飛び込んでくる外光を完全に遮りたいという理由がなければ、多少浮かせた状態でも覗き込めるわけです。
このあたり、化粧崩れを気にする女性に対して大きな訴求ポイントになるような気がするのですが、本体デザインが無骨すぎですかそうですか。
単純な蝶番構造ですが、90度ファインダーの角度を調節可能です。

背の低い三脚を使う時にも役に立ちますし、程よい硬さで角度を調整出来るので、撮影時にファインダーを頬などに当てて角度を微調整すると言った横着が可能です。

ファインダー装着時の大きさを考えると最初からミラーレスなり一眼レフなりを選べば良いじゃ無いか、という意見もありそうですが違うんですよねー。Nexus7やiPadにBluetoothキーボードをつけるなら最初からノートパソコンを使えば良いじゃないか、という論争と同じで。
ファインダーを使ってみて改めて気がついたG1X Mk2の操作性
先述しましたが背面液晶とEVFの表示切り替えが遅いので、ファインダーを覗き込んだ状態で可能な限り手探りで操作を行いたいのです。
切り替えが遅いという理由もさることながら、出来るだけ思考の流れを止めずにシャッターを切る所までたどりつきたい。
とした場合に、デュアルコントロールリングは最適な操作方法です。
また背面液晶右手の操作パネルが、他のPowershotシリーズと比較するとわずかにボタン起伏が大きく、また表面をなぞったときの指滑りがよく、目的のボタンを指の感触で探り当てやすいのです。

ビューアーとしても優れているEVF
撮影済みの写真や動画をEVFで見るのは非常に楽しい。背面液晶で見るよりもEVFの方が綺麗に見えるんじゃないかと思えるほど。
ビューアー的な使い方をする際に、ファインダーが可動してくれるのも地味に便利なんですよね。
というかEVF初心者なのでよくわからないんですけどEVFで画像を見ると立体感が増して見えるような気がするんですけど、なんぞこれ。
EVFとOVFのメリットデメリットって色々とあると思いますが、こういった使い方はEVFならではでしょうね。
まとめ的な
日々ぶつくさ言いながら使ってるこのカメラですが、オプションを色々と揃えたいと思うほどに気に入って使っています。
via PressSync