 Raspberry Pi
Raspberry Pi ポート開放・固定IP不要!Raspberry PiとDocker、Cloudflare Tunnelで作る、堅牢でハイメンテな自宅WordPressサーバー
0. この記事で構築するもの家に眠っている古いRaspberry Piを、安全で実用的なWebサーバーとして蘇らせてみませんか?この記事では、Raspberry Pi 3B+、Docker、そしてCloudflare Tunnelを組み合わ...
 Raspberry Pi
Raspberry Pi  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類 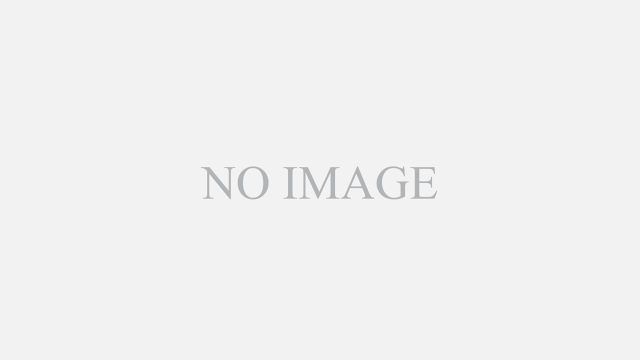 未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類 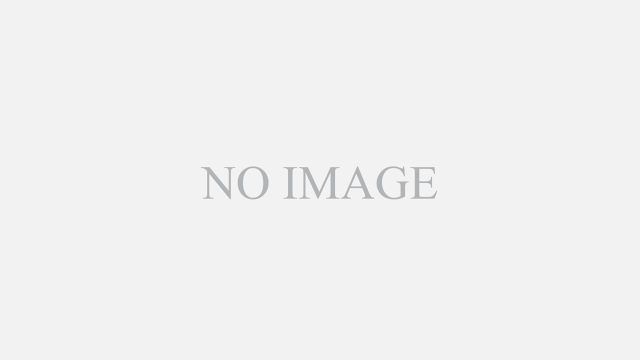 PressSync
PressSync